被爆、差別、階級、国家と戦争。井上光晴の作品を読み進めていると、どこか身体の奥がヒリヒリしてくるような感覚がある。決して「気持ちのいい」読書ではないが、戦後という時代の暗い底をここまで真正面から見つめた作家はそう多くない。
この記事では、そんな井上光晴の代表作・関連作を15冊にしぼって紹介する。部落差別と原爆後遺症が交差する長編から、原発と核廃棄物を扱った先駆的〈核〉文学、青春群像から詩集まで、振れ幅の大きいラインナップだ。どこから読めばいいかのガイドも用意したので、自分の気持ちや関心にいちばん近い一冊から手を伸ばしてみてほしい。
- 井上光晴とは?──「辺境」から世界の暴力を撃ち抜いた作家
- 読み方ガイド──最初の一冊はどれにする?
- 井上光晴のおすすめ本15選
- 1. 地の群れ(長編小説)
- 2. 死者の時(長編+「ガダルカナル戦詩集」)
- 3. 明日 一九四五年八月八日・長崎(長編小説)
- 4. 虚構のクレーン(長編小説)
- 5. 書かれざる一章(短編/初期代表作)
- 6. ガダルカナル戦詩集(詩的散文集)
- 7. 眼の皮膚(短編集)
- 8. 輸送(中編/「西海原子力発電所/輸送」収録)
- 9. 心優しき叛逆者たち(長編小説)
- 10. 階級(長編+短編収録)
- 11. 動物墓地(作品集)
- 12. 黒い森林(長編小説)
- 13. 小説の書き方 (新潮選書)
- 14. 全身小説家: もうひとつの井上光晴像 製作ノート・採録シナリオ
- 15. ひどい感じ──父・井上光晴 (講談社文庫)
- 関連グッズ・サービス
- まとめ──「辺境」から世界を見直すための15冊
- よくある質問(FAQ)
- 関連記事
井上光晴とは?──「辺境」から世界の暴力を撃ち抜いた作家
井上光晴は1926年生まれ。幼くして両親を中国で失い、その後は佐世保や伊万里、炭鉱の町・崎戸など九州各地を転々としながら育った。高等小学校中退後に海底炭鉱で働きつつ受験資格を得たという出自からして、すでに「辺境」から社会を見つめる視線が刻まれている。
戦後すぐに日本共産党へ入党し、九州地方の常任委員を務めながらガリ版詩集『むぎ』や共著詩集『すばらしき人間群』を刊行。やがて党内のスターリン主義批判に立ち、短編「書かれざる一章」などが問題作として批判され、最終的に離党する。政治運動の内部矛盾とそれを突き抜けようとする苛烈な倫理意識は、生涯にわたる小説世界の大きな核になった。
上京後は週刊誌記者などを経て作家専業に入り、「虚構のクレーン」や被差別部落と原爆被害を描いた『地の群れ』によって注目を集める。天皇制、原爆、炭鉱、朝鮮戦争、原発、階級対立といった、戦後日本が目をそらしがちな領域に執拗に光を当てたことから、「原爆文学」「炭鉱文学」「核文学」などの代表的作家として語られてきた。
同時に、彼は「物語の書き方」そのものを揺さぶる実験家でもあった。巨大な長編『心優しき叛逆者たち』のように時間と空間を細かく断片化し、複数の人物の視線を折り重ねる構成や、短編集『動物墓地』で見られる形式の解体など、読み手の「物語の常識」を揺さぶる作品も少なくない。
また、作家としての生涯そのものが「虚構」に満ちていたこともよく知られている。経歴や出生地をあえて曖昧に語り、後年にはドキュメンタリー映画『全身小説家』で、その嘘と真実が暴かれていく。その姿は、人生そのものを一つの物語として演じ続けた作家のあり方を示しているようでもある。
娘である小説家・井上荒野が、父と瀬戸内寂聴との関係をモチーフに『あちらにいる鬼』を書いたことも含めて考えると、井上光晴は「個人的な人生」「政治」「歴史」「文学」が濃密に絡み合った存在だとわかる。その複雑さゆえに、とっつきにくさを感じる人もいるかもしれないが、一冊でも読み終えると、戦後日本を見るときの視界が確実に変わる作家だ。
読み方ガイド──最初の一冊はどれにする?
作品世界が重く、どこから入るか迷う人も多いと思う。ざっくりとした「入口」をいくつか挙げておく。
- 社会の暗部も文学の厚みも一気に味わいたい → 『地の群れ』
- 戦争文学としての代表作を押さえたい → 『死者の時』
- 原爆文学に正面から向き合いたい → 『明日 一九四五年八月八日・長崎』
- 原発・核問題と現代の課題を考えたい → 『輸送』(「西海原子力発電所/輸送」所収)
- 作家の原点や政治との距離感を知りたい → 『書かれざる一章』
- まずは詩から静かに入りたい → 『荒れた海辺』
ここから先は、一冊ずつじっくり紹介していく。体力があるときに腰を据えて読む作品が多いので、読むタイミングも含めてイメージしながら選んでみてほしい。
井上光晴のおすすめ本15選
1. 地の群れ(長編小説)
『地の群れ』は、長崎・佐世保近郊の被差別部落と被爆者集落を舞台に、戦後日本の「見えない境界線」をえぐり出した代表作だ。朝鮮人の少女を妊娠させながら逃げた過去を持つ医師・宇南、そのもとに通う原爆病と思しき少女と、その母、被爆者集落「海塔新田」の人々……。差別と偏見が複雑に絡み合う土地で、彼らの過去と現在が次第に絡まり、憎悪が炎のように燃え広がっていく。
読んでいて最初に圧倒されるのは、土地の重みだ。海と山に囲まれた閉ざされた地形、炭鉱の衰退で仕事を失った人々、被爆者集落とそうでない地区のあからさまな分断。井上はその風景を、説明的な描写ではなく、登場人物の視線や会話の隙間からじわじわ立ち上げる。知らないはずの土地なのに、読み進めるほどに空気の匂いまで分かってくるような不思議な感覚になる。
物語の中心にあるのは、「差別されることを恐れて、自分の傷を認めない」人間の弱さだ。被爆者だと思われたくない母親が、娘の病を頑なに否定し続ける姿は、読む側の心を締め付ける。同時に、差別する側も、かつて誰かを裏切り、今も後ろめたさを抱えたまま生きていることが少しずつ明かされていく。善悪で割り切れる人物はほとんどおらず、全員が「加害者であり被害者」という地点に立たされる。
ときどき、あまりの重さにページを閉じたくなる瞬間がある。それでも読み続けさせるのは、井上の文体が、怒りだけでなく、どこか人間への諦めきれない愛着を含んでいるからだ。登場人物たちの言葉の端々に、どうしようもなさと同時に、小さな優しさが確かに残っている。
この作品は、「差別」や「原爆」という大きなテーマを学術書としてではなく、具体的な生活の手触りとして感じたい人に向いている。自分の中にある偏見や、見て見ぬふりをしてきた過去と向き合う覚悟があるときに読むと、強烈な読後感が残る一冊だ。
2. 死者の時(長編+「ガダルカナル戦詩集」)
『死者の時』は、太平洋戦争末期の特攻基地と、部落出身の霊媒師を軸に、「生き残る者」と「死者」の境界を見つめた戦争文学だ。特攻出撃を目前にした青年将校たちは、国家、天皇、恋人、死について考え続ける。一方、部落出身であることを隠しながら戦死者の「霊媒」を行う男や、夫の出征後にその部下と抱き合って孤独を紛らわせる人妻など、戦時下を生きるさまざまな人々の姿が描かれる。同書には、ガダルカナル島の飢餓と極限状況を綴った「ガダルカナル戦詩集」も収録されている。
この作品の印象的なところは、「戦場そのもの」よりも、「死を待つ時間」がひたすら描かれる点だ。出撃命令を待ちながら、隊員たちは、国のために死ぬとはどういうことか、本当に自分はそれを信じているのか、と自問自答を繰り返す。その思考の揺れが細かく追われることで、戦争の狂気が「どこか遠くの異常事態」ではなく、「少し条件が違えば自分もそこにいたかもしれない場所」として迫ってくる。
霊媒師の男の存在も強烈だ。部落出身であることをひた隠しにする彼は、戦死者の声を媒介する役割を負わされながら、自分自身もまた「死者の側」に片足を突っ込んでいるように描かれる。戦争、国家、階級というテーマが、彼の身体と仕事にすべて集中してしまっているように見えて、読みながら複雑な感情に揺さぶられる。
「ガダルカナル戦詩集」は、詩的散文のかたちで戦場の飢餓と崩壊を描いた実験作だが、むしろ『死者の時』全体を一種の「長い詩」として読ませる役割を担っている。散文と詩のあいだを行き来する文体が、戦争という出来事の「言葉にならなさ」をそのまま刻みつけてくる。
戦争文学に慣れていないと、読んでいて相当しんどい作品だと思う。それでも、「戦死者をどう悼むのか」「国家に命を捧げるとは何か」という問いを他人事ではなく考えたいとき、この本は避けて通れない。読後も、ふとした拍子に場面がよみがえってくるような、長く残る一冊だ。
3. 明日 一九四五年八月八日・長崎(長編小説)
『明日 一九四五年八月八日・長崎』は、そのタイトル通り、原爆投下の前日・1945年8月8日の長崎を描いた長編だ。結婚式を挙げたばかりの新郎新婦、刑務所に収監された夫に面会に向かう妻、難産の末に子どもを産む妊婦など、さまざまな人々の「その日」が、交錯しながら描かれる。彼らは翌日に自分たちを襲う運命を知らない。ただ、ごく普通の喜びや不安や苛立ちを抱えながら、いつも通りの日常を生きている。
この小説の怖さは、「原爆そのもの」はほとんど描かれないのに、ページの向こう側に常に「明日」が見えてしまうところにある。読者だけが、彼らの運命を知っている。その非対称な位置から読むことで、一つひとつの日常風景が、かえって痛ましいほど美しく見えてくる。たとえば、ささやかな祝言の場面や、子どもを迎え入れるための準備の描写。どれも「明日には消えてしまう」ことを知っているからこそ、胸に刺さる。
井上はここでも、被爆の悲惨さを直接的な描写で訴えるのではなく、「その直前」を徹底的に書き込むことで、核の脅威と人間の存在意義を問うている。結果として、原爆の場面が来る前に、すでに読者の心はかなり消耗しているはずだ。けれどその疲労感こそが、作品が突きつけてくる「問い」を受け止めた証拠でもある。
原爆文学を読んだことがない人にとっては、『はだしのゲン』などと比べると、とっつきにくく感じるかもしれない。ただ、「悲惨な場面を見る」タイプの作品ではなく、「失われる日常に寄り添う」作品として読むと、一気に印象が変わる。静かな読書の時間を確保できるときに、じっくり向き合いたい一冊だ。
4. 虚構のクレーン(長編小説)
「虚構のクレーン」は、日本共産党内部の矛盾やスターリン主義批判を題材にした長編で、『地の群れ』以前に井上の名を知らしめた作品だとされる。資料的には、党の下部組織で活動する人々の生活や、彼らが抱く疑問や葛藤が描かれており、のちに離党する井上自身の問題意識が色濃く反映されているとされる。
この作品を読む面白さは、「政治小説」としてだけでなく、「組織と個人の物語」として読めるところにある。革命の理想を掲げながらも、内部では権力争いや自己保身がうごめき、疑問を口にする者は排除されていく。プロジェクトや組織で働いた経験がある人なら、時代も文脈も違うのに、どこか身に覚えのある空気を感じるはずだ。
また、「虚構」というタイトルが示すように、ここでは「物語の作り方」へのメタ視線も強い。組織が語る「公式の物語」と、その裏で個人が抱える感情や記憶。そのギャップを埋めようとする言葉の運動そのものが、作品のテーマになっているように感じる。
政治やイデオロギーに特別関心がなくても、「正しいと信じていた組織に違和感を覚えたことがある人」には刺さる小説だと思う。現代のSNS空間での「正しさ」をめぐる断絶とも重ねながら読むと、予想以上に今の話として響いてくる。
5. 書かれざる一章(短編/初期代表作)
「書かれざる一章」は、1950年に文芸誌「新日本文学」に発表された、井上の事実上のデビュー作にあたる短編だ。日本共産党の下部党員たちの日常と活動を描いたこの作品は、党内から激しい批判を浴び、のちの離党とスターリン主義批判へとつながっていく。
物語として描かれるのは、革命という大きな理念ではなく、会議の準備やビラ配り、仲間同士の人間関係といった、ごく小さな日々の断片だ。そのささやかな場面の積み重ねから、「正しさ」を掲げる組織が、個人の感情や欲望をどう抑え込み、歪めてしまうのかが静かに浮かび上がる。
短編ということもあり、文章は後年の大長編ほど複雑ではない。それでも、すでにここで「階級」「組織」「性と革命」といったモチーフが顔を出しているのが分かる。初期作品を読みながら、のちの『地の群れ』や『階級』へと続く道筋を探る読み方も楽しい。
分量が手頃なので、「とりあえず井上光晴の原点だけ味わいたい」という人の入口にも向いている。思想的な背景に関心があるなら、この作品を読んでから論評や評伝に広げていくと、作家像の輪郭が一気に鮮明になるはずだ。
6. ガダルカナル戦詩集(詩的散文集)
「ガダルカナル戦詩集」は、その名の通りガダルカナル島の戦いを題材にした詩的散文で、『死者の時』と同じ巻に併録されていることが多い。飢餓と極限状況のなかで崩れていく兵士たちの身体と精神を、叙情と残酷さが入り混じった文体で描き出した作品だ。
通常の小説のように筋を追うというより、一連のイメージやモチーフを浴びるように読むと、作品の輪郭が見えてくる。泥、骨、腐臭、熱帯の光。そうした感覚的なイメージが、戦争という出来事を美化することなく、しかし単に「悲惨」の一語に押し込めることもなく、複雑な層を持ったものとして伝えてくる。
詩や実験的な散文に抵抗がない人なら、むしろこの作品から入ってもいい。戦争を扱った報道写真やドキュメンタリーに慣れた目で読むと、「戦争を言葉にするとはどういうことか」という根本的な問いが改めて突きつけられる。
7. 眼の皮膚(短編集)
『眼の皮膚』は、講談社文芸文庫版では短編「遊園地にて」と一緒に収められた短編集で、何げない日常の風景の背後に潜む不安や恐怖を描いた作品群だ。表題作「眼の皮膚」では、一見幸せそうな夫婦と子どもの生活の「背後」に、得体の知れない戦慄がじわじわとにじみ出してくる。
ここでは、あからさまな政治や戦争のモチーフは前面には出てこない。その代わり、団地や遊園地といった戦後の「普通の生活空間」の中に、井上らしい闇が顔を出す。たとえば、ふとした拍子に見える他人の視線や、説明のつかない違和感が、読み手自身の生活にも通じる感覚として迫ってくる。
長編に比べると分量がコンパクトなので、まずは短編で文体や雰囲気に慣れたい人に最適だ。ホラーやサスペンスとは違う形での「怖さ」を味わいたいとき、静かな夜にじっくり読みたい一冊でもある。
8. 輸送(中編/「西海原子力発電所/輸送」収録)
「輸送」は、講談社文芸文庫『西海原子力発電所/輸送』に収められた中編で、核廃棄物輸送事故による被曝と避難生活の破壊を予見した〈核〉文学だ。原子力発電所を抱える閉鎖的な地域社会と、そこで起きた不審火事件を描く「西海原子力発電所」とともに、原爆と原発を深く結びつけた記念碑的な作品と評価されている。
チェルノブイリ事故後に書かれた「輸送」は、核廃棄物の輸送事故による被曝や避難生活が、どのように人々の日常を破壊していくかを、きわめて具体的に描いている。その描写は、3・11以降の福島第一原発事故を経験した私たちから見ると、予言的とすら感じられる部分が少なくない。
ここでも井上は、「善悪二元論」に落とし込むことを避ける。原発に経済的に依存せざるをえない地域の事情、反対運動の側にある不純さ、無関心な都市生活者の視線など、どの立場にも「言い分」と「弱さ」があることを描きながら、それでもなお核の危険性は覆い隠せないという現実を突きつける。
原発問題について、ニュースや解説書だけでなく「小説として」考えてみたい人には、強くすすめたい作品だ。読み終えたあと、ニュース映像で見る「使用済み核燃料」「処理水」といった言葉の重さが、確実に変わっているはずだ。
9. 心優しき叛逆者たち(長編小説)
『心優しき叛逆者たち』は、1969年5月の東京(新宿、下北沢、野方、下落合など)を舞台に、三日間の出来事を原稿用紙1400枚という途方もないボリュームで描いた長編だ。右翼の父とその一族に反発して大学を中退した錬若四郎、女に目がない詩人の左門長兵衛、かつて男を刺して服役した過去を持つ江府安子、朝鮮人の父を持つ李陣春子ら、四人の若者を中心に、数え切れない人々の人生が交錯していく。
タイトルにある「心優しき」という形容が、この小説を読む鍵になる。叛逆と聞くと、激しい怒りや破壊衝動を思い浮かべがちだが、井上が描く叛逆者たちは、どこまでも「誰かを傷つけたくない」「ちゃんと愛したい」と願ってしまう人たちだ。だからこそ、社会の不条理や暴力を前にしたとき、彼らの戸惑いは一層深くなる。
物語は直線的には進まず、時間と空間が細かく切り替わっていく。最初は読みづらさを感じるかもしれないが、その断片の積み重ねが、ある時点で一つの大きなうねりとして見えてくる。60年代末という時代の空気──学生運動、政治闘争、性の革命──を、「歴史的事件」ではなく、名前を持った個々の人間の感情の集積として体感させてくれる。
体力の要る大作だが、「怒りと優しさが矛盾なく共存する叛逆」というテーマに惹かれる人には、ぜひ挑戦してほしい一冊だ。
10. 階級(長編+短編収録)
『階級』は、現代社会の〈辺境〉とも言える廃鉱に「遺棄」された人々を描いた長編で、炭鉱離職者をテーマにした短編「せむしたちの冬」も収録されている。廃鉱に押し込められた人々の「階級的憎悪」の情念と、人間破壊の状況が、読者に異様な衝撃と戦慄を与える作品だと紹介されている。
ここで井上が見つめているのは、「貧しいからこそ連帯する」美しい階級意識ではなく、「傷つけられ続けた結果としての憎悪」だ。炭鉱閉山後、社会から切り捨てられた人々の間に渦巻くのは、単純な「被害者の連帯」ではなく、互いへの嫉妬や軽蔑、過去のしがらみといったドロドロした感情だ。
読む側にとっても居心地のいい物語ではないが、「階級」という言葉をスローガンではなく生身の感情として考えたいなら、この作品は貴重なテキストになる。現代日本でも、地方の「さびれた街」や非正規雇用の問題を思い浮かべながら読むと、決して過去の話ではないと気づかされるだろう。
11. 動物墓地(作品集)
『動物墓地』は、タイトルどおり「動物」「墓地」といったモチーフを通して、管理社会の不条理や現代人の孤独を描いた作品集だ。批評的には、この本で井上が小説のスタイルを徹底的に解体し続けていることが指摘されている。主流の物語形式に対するアンチテーゼとしての実験が、一冊まるごと展開されていると言っていい。
ストーリーを追うよりも、「こんな書き方もあるのか」という驚きとともに読むタイプの本だと思う。動物園や墓地といった象徴的な空間は、どこか「いまの社会」そのものの比喩として立ち上がってくる。管理され、名前を与えられ、分類される存在としての人間。その居心地の悪さが、じわじわと染み込んでくる。
物語のわかりやすさを求める読者には向かないが、「小説の形式に興味がある」「実験的な作品が好き」というタイプなら、一度は触れてみたい一冊だ。
12. 黒い森林(長編小説)
『黒い森林』は、強制収容所帰りの元作家を軸に、社会主義国家・ソ連における非合法な地下出版を描いた長編だ。秘密の地下出版と強制収容所を通して、人間の原存在を脅かす暴力を烈しく告発した異色作とされている。
井上はここで、日本国内の問題から一歩外へ出て、「社会主義」の名のもとに行われる抑圧と暴力を描いている。ただし、それは決して「外国の話」として距離を取れるものではない。検閲、自己検閲、言論統制、そして「正しい言葉だけが許される」社会の息苦しさ──その多くは、形を変えてどんな社会にも現れうるものだ。
作中で描かれる作家たちの葛藤や、地下出版に関わる人々のリスクは、現代のネット社会で「炎上」を恐れながら言葉を選んでいる私たちの姿とも、どこか重なって見える。政治体制や時代は違っても、「言葉の自由」をめぐる問題はつねに現在進行形なのだと、あらためて思い知らされる作品だ。
13. 小説の書き方 (新潮選書)
タイトルだけ見ると、いかにも「テクニック集」や「構成マニュアル」を想像してしまうが、『小説の書き方』はもう少し体温の高い本だ。紀伊國屋ホールで行われた連続講演をもとに加筆された内容で、いわゆるハウツーというより、「自分の体験をどう言葉に変えていくか」をめぐる長い告白のように読める。日々風化していく体験をどう生かすか、現実が想像力を追い越していく時代に、どうやって想像力の質を鍛えるか――そんな問いが、講義口調の語りのなかに繰り返し浮かんでは沈んでいく。
この本で特に有名なのが、「三冊ノート」の方法だ。日常に起こった出来事だけを書きつけるノート、その日に読んだものや考えたことを書くノート、そして完全な作り話だけを書くノート。見開きの片ページだけを埋めて、もう片側は空白のままにしておき、ひと月ほど経ってから、その「空白」を使って新しい物語をふくらませていく。地味な作業だが、これを一年続ければ、物語を構成する想像力の質は飛躍的に変わる、と井上は言い切る。
読んでいて面白いのは、ここで語られているのが「効率よくデビューする方法」ではないことだ。むしろ、「どれだけ回り道を引き受けるか」「どれだけしつこく自分の体験を追い回すか」という話に終始している。流行ジャンルや投稿サイトの攻略法ではなく、「自分の人生を、小説という形式に耐えうる素材に変質させるまで寝かせる」という、気の遠くなるような時間感覚が前提になっている。
個人的には、「日記はそのままでは小説にならない」というくだりが刺さった。感情をそのまま書き散らかしたノートは、一見生々しいが、他人にとっては単なる記録でしかない。そこから一度距離を取り、時間を置いて発酵させ、別の形に組み立て直すところに、フィクションの本当の作業がある。その説明を読んでいると、自分の昔の日記帳をもう一度開き直してみたくなる。
これから書き始めたい人にとっても、すでに書いている人にとっても、この本は「やることを増やす」のではなく、「戻る場所をひとつ増やしてくれる」タイプの本だと思う。行き詰まりを感じたときに、机の脇から抜き出して、ぱらぱらと数ページ読むだけでも、自分の書いてきたものの手触りが少し変わる。もしあなたが、「何を書けばいいのか分からない」と悩んでいるなら、この本は「すでに持っているものを掘り起こす」ためのスコップとして機能してくれるはずだ。
14. 全身小説家: もうひとつの井上光晴像 製作ノート・採録シナリオ
『全身小説家: もうひとつの井上光晴像 製作ノート・採録シナリオ』は、原一男監督のドキュメンタリー映画『全身小説家』の製作過程と、採録シナリオをまとめた一冊だ。ガンで亡くなった「異能の作家」井上光晴の、生と文学の原点での相克を追いかけた映画の舞台裏が、詳細なノートと台本のかたちで残されている。単なる映画パンフレット拡大版ではなく、「一人の作家の虚構と現実に、カメラがどこまで踏み込めるか」をめぐる、もう一つのドキュメンタリーとして読める本だ。
製作ノート部分には、撮影の意図や躊躇、撮られる側との駆け引きが、かなり生々しく書き込まれている。井上がこれまで語ってきた〈経歴〉──旅順生まれ、炭鉱での労働経験、さまざまな武勇伝──の多くが実は虚構であったこと、その虚構を暴くことが本当に「正義」なのかどうか、カメラを向ける側の良心が揺れる瞬間も含めて記録されている。
採録シナリオを読むと、映画で見た場面のテンポや間合いが、文字情報として立ち上がってくる。インタビューの一言一句、沈黙の長さ、部屋の空気。映像では一瞬で流れていってしまう細部が、セリフとして固定されることで、改めて「この人はこういう言い回しをするのか」「ここで笑うのか」といった発見がある。井上の作品を読んできた人なら、その言葉遣いにどこか既視感を覚える瞬間もあるだろう。
面白いのは、この本を読むと、井上光晴の「嘘」そのものへの評価が単純ではいられなくなるところだ。経歴を盛ることはもちろん許されることではないが、その嘘はどこかで作品世界とつながっている。自分の出自を「物語化」して初めて耐えられる何かがあったのではないか、と考え始めると、単純な告発では済まない複雑さに引き込まれていく。
映画『全身小説家』を未見でも、この本だけで一つの読み物として成立しているが、できれば本と映画を往復しながら味わいたい。活字の井上光晴、映像の井上光晴、そのどちらもを撮ろうとして揺れる原一男。三者のあいだに張り詰めた緊張感が、ページごとに滲み出てくる。作家という存在そのものをめぐるメイキングとして、かなり稀有な一冊だと思う。
15. ひどい感じ──父・井上光晴 (講談社文庫)
『ひどい感じ──父・井上光晴』は、小説家・井上荒野が、自身の父である井上光晴について書いたノンフィクションだ。講談社から単行本として刊行されたのち、講談社文庫にも入っている。没後十数年を経てもなお多くの人に語られ続ける作家・井上光晴。その生涯が謎と虚構に包まれていたこと――旅順生まれ、炭鉱労働、さまざまな経歴の「嘘」――を踏まえたうえで、娘の視線から「父」を描き直していく本でもある。
タイトルにある「ひどい感じ」という言葉が、読み進めるほどに妙な味わいを帯びてくる。夫としても父としても、光晴ははっきり言って破天荒で、しょっちゅう家を空けるし、女性関係の問題も山ほどある。普通に考えれば「ひどい父親」なのに、なぜか完全には嫌いになれない。ひどいことを繰り返しているのに、そのほとんどを相手も承知していて、それでもなお人を惹きつけてしまう。そのアンバランスさが、「ひどい感じ」という一言の中にきれいに収まっている。
娘であり、同じく小説家でもある井上荒野の語り口は、感傷に流れず、かといって冷笑でもない。幼い頃の記憶や、大人になってからの同居生活、がん闘病の時間などが、淡々とした文体で綴られていく。ときどき出てくる、父のどうしようもなく情けないエピソードに、くすっと笑ってしまい、同時に、笑ってしまった自分の感情に少し戸惑う。
印象的なのは、「父親」という役割からどうしてもはみ出してしまう人物を前にしたとき、家族の側がどう折り合いをつけていくのか、という視点だ。安定した家族像の雛形を持たないまま、「まともな父親」というものへのスタンスがどこか屈折した男を相手に、娘はどう距離を取るのか。そこには、父と娘の物語であると同時に、「家族とは何か」という問いが静かに流れている。
井上光晴の作品をある程度読んだあとでこの本を手に取ると、小説のなかの人物たちの輪郭が微妙に変わって見えてくる。作品世界に漂っていた「父親不在」や「家の不安定さ」が、単なるモチーフではなく、かなり生々しい現実から来ていたのだと気づかされるからだ。逆に、まずこの本から読み始めて、そのあとに『地の群れ』や『死者の時』へ入っていく、という順番もおもしろいと思う。
父と子どもの距離感に悩んでいる人や、「親のことを好きとも嫌いとも言い切れない」という気持ちを抱えている人には、かなり刺さる一冊だろう。読み終えたあと、自分と親との関係にも、どこか「ひどいけれど、完全には切り捨てられない何か」があることに、ふと気づいてしまうかもしれない。
関連グッズ・サービス
本を読んだ後の学びを生活に根づかせるには、生活に取り入れやすいツールやサービスを組み合わせると効果が高まる。
井上光晴の作品はどれも情報量と感情の振れ幅が大きいので、ゆっくり反芻する時間をつくりながら読みたい。そのための相棒として、いくつかアイテムを挙げておく。
長編や関連書をまとめてチェックしたいなら、まずはKindle Unlimitedのような読み放題サービスをひと月だけ試してみる手がある。井上光晴そのものだけでなく、同時代の作家や原爆・原発を扱ったノンフィクションを横断して読むと、作品世界の立体感が一気に増す。
通勤や家事の合間に関連書を耳で追いたいなら、Audibleのような音声サービスも相性がいい。たとえば戦争や原発を扱った評論・ルポルタージュを耳で聞きつつ、夜に井上の小説を読むと、現実と文学のあいだを行き来するリズムができてくる。
・読書用のルームウェアと温かい飲み物
『地の群れ』や『死者の時』のような重い作品は、一気読みよりも、夜に少しずつページを進める読み方が向いている。身体をゆるめるルームウェアに着替え、ハーブティーやコーヒーを入れて、「今日は一章だけ」と決めて読むと、精神的な負荷を少し和らげられる。差別や戦争を扱う作品だからこそ、自分のコンディションを整える道具をセットで用意しておきたい。
まとめ──「辺境」から世界を見直すための15冊
井上光晴の本を続けて読んでいると、自分が立っている場所の足元が、少しずつぐらついてくる感覚がある。被爆地や被差別部落、廃鉱、原発立地地域といった「辺境」に立つ人々の視線から社会を見直すことで、ふだんニュースや教科書の言葉では見えなかった断層がくっきりと露わになる。
差別、戦争、階級、核。どれも重いテーマだが、井上の作品はそれを「テーマ小説」としてではなく、生身の人間の感情と生活を通して描き出している。だからこそ、読者の側もまた、自分自身の生活や選択を見直さずにはいられなくなるのだと思う。
最後に、読書目的別に軽くおすすめをまとめておく。
- まず一冊だけ読むなら:『地の群れ』
- 戦争と死者の問題を深く考えたいなら:『死者の時』『ガダルカナル戦詩集』
- 原爆・原発と向き合いたいなら:『明日 一九四五年八月八日・長崎』『輸送』
- 60年代の空気と若者の心情を味わいたいなら:『心優しき叛逆者たち』
- 短編や詩から静かに入りたいなら:『眼の皮膚』『荒れた海辺』
読み終えたあと、しばらくは胸の奥がざわざわすると思う。そのざわめきを大事にしながら、自分なりの速度で、次の一冊に進んでいってほしい。
よくある質問(FAQ)
Q1. 井上光晴はどの作品から読むのがいちばんとっつきやすい?
物語としての読みやすさでいえば、『明日 一九四五年八月八日・長崎』や『眼の皮膚』あたりが入り口になりやすい。前者は原爆前日の一日を描く群像劇で、人物たちの感情に寄り添いやすい構成になっているし、後者は短編なので一編ごとに区切って読める。『地の群れ』や『心優しき叛逆者たち』は圧倒的な読み応えがある分、最初の一冊としてはややヘビーなので、二冊目以降に回すといいかもしれない。
Q2. 政治色が強そうで不安。思想や歴史に詳しくなくても読める?
確かに、共産党や階級闘争、原爆・原発など、政治的なテーマが前面に出てくる作品が多い。ただ、物語の中心にいるのは、いつも具体的な名前と顔を持った登場人物たちだ。政治思想の細かい文脈を知らなくても、「この人はなぜこんな行動をしてしまうのか」「なぜここまで追い詰められたのか」と考えながら読めば、十分に心を揺さぶられるはずだ。むしろ、読みながら気になったキーワードをあとで少しずつ調べていくと、自然に歴史や思想への理解が深まっていく。
Q3. 戦争や差別の描写が重そうで、最後まで読めるか心配…
無理に一気読みしようとせず、「今日はここまで」と決めて少しずつ読むのがおすすめだ。特に『地の群れ』や『死者の時』のような作品は、読み進めるだけでかなり精神力を消耗するので、休み休みでいい。どうしてもしんどくなったら、いったん離れて短編や詩集に移り、気持ちが戻ってきたときに再開すればいい。きちんと傷つきながら読むことでしか見えてこない風景があるので、自分のペースを守りつつ付き合っていくのがいちばんだ。
Q4. 他のどんな作家と一緒に読ぶと理解が深まる?
同時代の戦後派作家としては、大江健三郎や野間宏、また炭鉱や地方を描いた中上健次などと一緒に読むと、戦後文学のなかで井上がどんな位置にいるのかが見えてくる。原爆や原発というテーマからは、ノンフィクションとしてのルポルタージュや、福島原発事故を扱った記録類に並べて読むのも有効だ。複数の作家を横断して読むうちに、「戦後日本をどう描くか」という大きな問いが、自分の中にも立ち上がってくるはずだ。
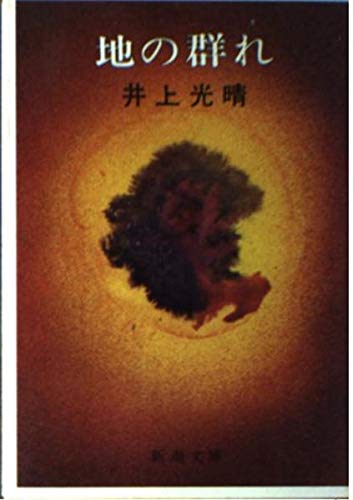







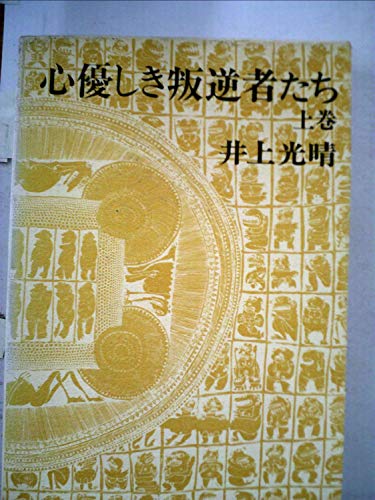








![[TENTIAL] BAKUNE スウェット ウィメンズ レディース リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ピンク M [TENTIAL] BAKUNE スウェット ウィメンズ レディース リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ピンク M](https://m.media-amazon.com/images/I/31BPGDmF+EL._SL500_.jpg)
![[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L [TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L](https://m.media-amazon.com/images/I/315csivXYtL._SL500_.jpg)



