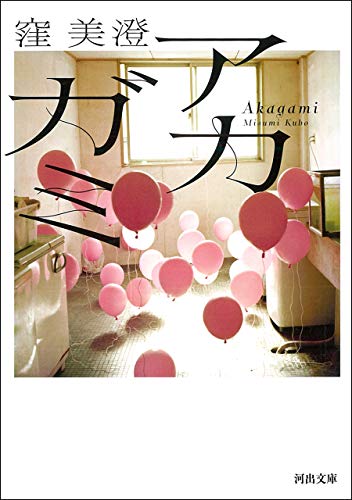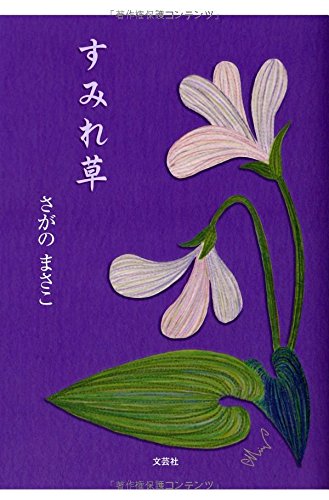愛情がこじれてしまった家族関係や、言葉にしづらい性と生の問題を、ここまで正面から描ききる作家はそう多くない。窪美澄の小説に触れると、「自分だけが壊れているわけじゃなかったのかもしれない」と、胸の奥で長く固まっていた何かが少しだけゆるむ。
ここでは、直木賞受賞作『夜に星を放つ』をはじめとする代表作22冊を紹介していく。
- 窪美澄とは? 喪失の先にある「生」を見つめ続ける物語作家
- おすすめ本22選
- 1. 夜に星を放つ
- 2. ふがいない僕は空を見た(新潮文庫)
- 3. トリニティ
- 4. 晴天の迷いクジラ(新潮文庫)
- 5. じっと手を見る(幻冬舎文庫)
- 6. さよなら、ニルヴァーナ
- 7. ははのれんあい
- 8. 夏日狂想
- 9. アカガミ
- 10. 朔が満ちる
- 11. 我らがパラダイス
- 12. アニバーサリー
- 13. 水やりはいつも深夜だけど
- 14. よるのふくらみ
- 15. タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース
- 16. いるいないみらい
- 17. すみれ草
- 18. 夜空に浮かぶ欠けた月たち (角川書店単行本)
- 19. 宙色のハレルヤ (文春e-book)
- 20. 私は女になりたい (講談社文庫)
- 21. 朱より赤く 高岡智照尼の生涯 (小学館文庫 く 18-1)
- 22. 給水塔から見た虹は (集英社文芸単行本)
- 窪美澄作品と一緒に使いたい関連グッズ・サービス
- 窪美澄を読むならどれから?──全体のまとめ
- よくある質問(FAQ)
- 関連記事
窪美澄とは? 喪失の先にある「生」を見つめ続ける物語作家
窪美澄は、現代日本の家族や共同体が抱えるひび割れを、性や暴力、貧困といった生々しいモチーフを通して描いてきた作家だ。デビュー作『ふがいない僕は空を見た』で山本周五郎賞と本屋大賞2位を射止め、その後も直木賞候補を重ねつつ、『夜に星を放つ』で第167回直木賞を受賞する。
彼女の作品世界には、いわゆる「いい人」はほとんど出てこない。みなそれぞれに身勝手で、弱く、時に誰かを傷つける。それでもなお、その人物たちの内側でうごめく後悔や諦めきれない願いに、読者はどうしようもなく共感してしまう。そこにこそ窪美澄のすごみがある。
背景にあるのは、平成から令和へと続く不安定な時代感覚だ。非正規雇用、格差拡大、介護や育児の負担、インターネット以降の「炎上」文化──彼女の小説は、そうした現実の細部を逃さず拾いあげる。だが同時に、「それでも人は誰かを愛そうとする」という、きわめて素朴な希望を手放さない。
文学の系譜でいえば、島本理生や桜木紫乃のような「女性の生と性」を描く書き手とも響き合いつつ、社会福祉やジェンダー論への鋭い視線も持ち合わせているのが窪作品の特徴だ。介護現場を舞台にした『じっと手を見る』や、高級老人ホームの裏側を描く『我らがパラダイス』などは、社会小説として読んでも手応えがある。
いま、この国でしんどさを抱えて生きている人ほど、窪美澄の小説は痛烈に刺さる。読後に残るのは、甘い癒やしではない。どちらかといえば、「それでも生き続けるしかない」という少し重たい覚悟と、それを支えるほんのわずかな灯りだ。その灯りを見に行くための入り口として、これから紹介する25冊はどれも信頼できる案内役になる。
おすすめ本22選
1. 夜に星を放つ
直木賞受賞作となったこの短編集は、「大切な人を失ったあと、人はどこへ行きつくのか」という問いを、五つの物語で変奏していく一冊だ。恋人を、家族を、友人を、あるいはかつての自分自身を失った人たちが、それぞれの夜をさまよいながら、ふとした瞬間に星の光のような記憶に照らし出される。そのまばゆさと痛みが、ページごとに胸へ刺さる。
印象的なのは、悲しみを「きれいごと」に逃がさないところだ。喪失の直後には、怒りやみっともない嫉妬、後悔が渦巻く。窪はそこを遠慮なく描く。だからこそ、登場人物たちがふと空を見上げる瞬間が、読者には決定的な出来事として届くのだ。星空そのものが、亡くなった誰かというより「失われた時間」そのもののように感じられる。
短編集なので、一話ごとに切れ目はある。それでも通して読むと、不思議な連作性が立ち上がってくる。誰かを喪った経験がある人なら、どこか一話は自分の物語だと感じるだろう。個人的には、夜遅くに一人でソファに座り、部屋の明かりを落として読んだとき、ページの白さが本当に星の光のように見えた。読み終えたあとも、その白さだけが目の奥に残っていた感覚をよく覚えている。
仕事や育児で日中は現実に追われている人にこそ、この本は夜の時間にそっと開いてほしい。短編なので少しずつ読んでもいいし、一気に読んで感情を揺さぶられてもいい。電子書籍派なら、寝る前にスマホやタブレットでKindle Unlimitedのラインナップを覗きながら、自分のペースで読み進めるのも悪くない。
「悲しみをちゃんと悲しめていない気がする」と感じている人にとって、『夜に星を放つ』は、自分でも言語化できなかった感情を代わりに言葉にしてくれる本になる。泣くためではなく、涙の根っこを確かめるために読む一冊だ。
2. ふがいない僕は空を見た(新潮文庫)
山本周五郎賞と本屋大賞2位を獲得したデビュー長編であり、窪美澄の名を一気に知らしめた代表作。不妊治療に悩む主婦と、貧しい高校生との情事という、あまりにもデリケートでセンシティブな題材を正面から描ききっている。あらすじを聞くだけならスキャンダラスだが、実際に読むと、そこにあるのはスリルではなく、どうしようもない孤独同士がすり寄る音だ。
性描写は決して少なくない。それでも、エロティックな高揚感というより、「こうでもしないと生きていけなかった」という切迫感が強い。誰かの妻であり母である女性が、「女」として求められることで自分をギリギリ保とうとする姿。まだ社会的には子どもでしかない少年が、「男」であろうとすることで、自分の弱さを隠そうとする姿。同じベッドの上にいながら、二人が見ている空はまったく違う。
この作品のすごさは、彼らの行為を「正しい/間違っている」で裁かないところにある。読者は、不快さややりきれなさを感じつつも、いつのまにか彼らの側に立ってしまう。なぜなら、家族や学校、社会が用意した「正しい生き方」のどこにも、自分の居場所がないと感じたことは、多くの人にとって身に覚えがあるからだ。
物語が進むにつれて、「ふがいない」のは誰なのか、という問いがじわじわと浮かび上がる。主人公の少年だけではない。彼を見て見ぬふりをする大人も、誰かを支えきれないまま自分を責め続ける母親たちも、みなそれぞれ自分のふがいなさを抱えて空を見ている。その構図に気づいたとき、タイトルの意味が少し変わって見える。
読書体験としては、かなり胃の痛くなる一冊だ。読んでいて何度も本を閉じたくなる。それでも最後までたどり着いたとき、「ここまで痛いところまで書いてくれてありがとう」と思ってしまう。不妊治療や性の問題に身近で触れてきた人ほど、簡単には語れない感情を突かれて、しばらく言葉を失うかもしれない。
ティーンエイジャーの読者に勧めるには少し覚悟がいるが、20代後半以降で、自分の生き方や家族との距離感に悩んでいる人には強烈に響く。ライトなエンタメではなく、思い切りえぐられたいときに開く本だ。
3. トリニティ
『トリニティ』は、1960年代から平成までの日本の出版業界を舞台に、三人の女性の人生を追いかける長編だ。「トリニティ(三位一体)」というタイトルが示すように、三人それぞれのキャリアと恋愛、家族のかたちが、時代の光と影を映しながら絡み合っていく。
面白いのは、「女の友情」をロマンチックにも冷笑的にも描かない点だ。三人は互いに励まし合いながらも、時に嫉妬し、距離を置き、また仕事で利害が交わる。若い頃は「同じ場所を目指して走っている」と信じていた仲間が、いつのまにか別の景色を見ている──そんな残酷さが、静かに積み重ねられていく。
出版業界という舞台装置も効いている。作家と編集者、営業、広告、書店……本をめぐる仕事には理想と現実が常に同居する。その中で、女性であること、母であること、妻であることが、どれほどキャリアの選択に影響してくるのか。窪は「女性活躍」というきれいなスローガンをなぞるのではなく、会議室の空気や、保育園の送り迎えの時間配分といったディテールを通して描き出す。
読んでいて何度か、胸がざらついた。自分より少し上の世代の働く女性たちの本音が、こんなふうに積み重なっていたのか、と。読者としては、三人のうち誰か一人に感情移入する、というより、その時々の自分の人生ステージによって寄り添う相手が変わっていくタイプの物語だと感じた。
ボリュームはあるが、文章は読みやすく、仕事小説としても家族小説としても楽しめる。出版業界に興味がある人はもちろん、今まさにキャリアの岐路に立っている30〜40代の女性読者には、とくに刺さるだろう。紙の本をじっくり読み込みたいタイプの人向けだが、通勤時間に少しずつ進めたいなら電子で分冊して読むのもいい。夜、仕事から帰ってきてから一章だけ読む、という読み方が似合う一冊だ。
4. 晴天の迷いクジラ(新潮文庫)
タイトルからして一筋縄ではいかないこの作品は、「死に場所を探す」若者と、「もう人生の出口に近い」と感じている老婆たちが、奇妙な共同生活を送ることになる物語だ。海辺の家という舞台設定もあり、どこか現実から少しだけ切り離された「避難所」のような空気が漂う。
この小説に出てくる人物たちは、みな生きることにうんざりしている。仕事もうまくいかない、家族とも折り合えない、未来を思い描けない。そんな人たちが同じ屋根の下で暮らし始めると、当然摩擦も起きる。ときには醜い感情がむき出しになる。それでも一緒にご飯を食べ、天気やテレビ番組の話をし、誰かが体調を崩せばなんとなく看病する。その「なんとなく」が、読んでいてたまらなく愛おしい。
クジラというモチーフは、現実の海にいる巨大な生き物というより、彼らの心の中にある「どこにも行き場のない塊」に近い。晴れた日にふと、遠くの海にそのクジラが浮かび上がるように感じる瞬間が、物語の中に何度か訪れる。そのたびに、読者も自分自身の「迷いクジラ」の存在を意識させられる。
個人的には、読後感がとても不思議な作品だった。救いがあると言えばあるし、ないと言えばない。誰かが劇的に変わるわけではなく、彼らの明日は相変わらず不安定だろう。けれど、読者としては「それでも、この人たちはきっと明日も起きてご飯を食べる」と、なぜか確信してしまう。その程度の小さな希望が、本当に尊いものに思えてくる。
人生のどこかで「消えてしまいたい」と思った経験がある人には、危ういほど刺さるかもしれない。落ち込んでいるときに軽く読む本ではないが、ある程度気持ちが戻ってきたタイミングで、自分の過去を振り返るような気持ちで開くと、そっと背中をさすってもらったような感覚が残るはずだ。
5. じっと手を見る(幻冬舎文庫)
タイトルは石川啄木の有名な短歌から取られているが、ここでじっと手を見るのは、現代の介護士たちだ。介護現場で働く若者たちの日常と心の揺れを描いた連作短編集で、窪美澄の社会小説としての側面がよく表れている。
介護の仕事は、「やりがい」と「自己犠牲」がごちゃごちゃに混ざりやすい。そのうえ賃金は低く、シフトは不規則で、心身ともにすり減りがちだ。この本に出てくる若者たちは、決して「立派な福祉マン」ではない。楽な仕事を探してやめていこうとする者もいれば、利用者に苛立ちを抑えきれない者もいる。それでも彼らが、ふとした拍子に利用者の手を握られたり、忘れられない一言をかけられたりして、もう少しだけ続けてみようと思ってしまう、その瞬間が丁寧に描かれている。
連作形式なので、一人ひとりのエピソードが積み重なっていくうちに、ひとつの施設の空気が立ち上がってくる。仕事の愚痴を言い合う休憩室、夜勤明けのぼんやりした頭、家に帰っても家族のケアを担わされる若い女性──そうした風景があまりにもリアルで、介護の現場を知らない読者でも、そこに自分の職場を重ねてしまうかもしれない。
「じっと手を見る」という行為は、働く自分の手を見つめながら、「この先、自分はどうやって食べていくんだろう」と考える時間そのものだ。ここに描かれているのは、介護士だけの話ではない。非正規で働くコンビニ店員も、コールセンターのオペレーターも、みなそれぞれ「自分の手」を見ている。その普遍性が、この本を単なる「介護小説」にとどまらないものにしている。
介護職に就いている人や、これから福祉の仕事を考えている学生にはもちろん、お金のために働き続けることに疲れているすべての人に手渡したくなる一冊だ。読みながら、何度も自分の手を見てしまうはずだ。
6. さよなら、ニルヴァーナ
かつて社会を震撼させた「少年A」を崇拝する少女、娘を殺された母親、その事件を小説として描こうとする作家。『さよなら、ニルヴァーナ』は、加害と被害、そしてそれを物語にする行為の倫理を、真正面から問う重い一冊だ。
この小説のすごさは、「事件の真相」ではなく、「事件の周りに残された人々の物語」にフォーカスしている点にある。加害者に魅了される少女の内面は、単純な「病んだ若者」では片づけられない複雑さを持つ。彼女の崇拝は、どこか信仰にも似ていて、読んでいて背筋が寒くなる。一方で、被害者遺族の母親は、「許せない」という感情と、「憎しみにとらわれ続けている自分」への嫌悪との間で揺れ続ける。
そこに、作家という第三者の視点が入ってくることで、読者は自分自身の立ち位置も問われることになる。自分はこの物語を「安全な場所」から読んでいるだけなのではないか。誰かの悲劇を消費しているのではないか。そうしたメタな問いが、じわじわと滲んでくる。
タイトルにある「ニルヴァーナ」は、仏教的な涅槃であり、同時にロックバンドの名前も連想させる。そこには、「完全な救済はどこにもないのだろう」という諦念と、「それでもどこかに出口を探したい」という願望が同居しているように思える。物語の終盤に近づくにつれ、「さよなら」と言うべき相手が誰なのか、読者の中で何度も書き換えられていく。
決して軽く勧められる本ではないが、事件報道に触れるたびにモヤモヤを抱えてきた人には、一度読んでおいて損はない。感情を揺さぶられるだけでなく、「自分は何を知りたかったのか」「何を見ないようにしてきたのか」を考えさせられる、かなりハードな読書体験になる。
7. ははのれんあい
『ははのれんあい』は、夫の裏切りによって壊れかけた家族と、そこで新しい恋に踏み出そうとする母親、そして彼女を見つめる息子たちの視点が交錯する家族小説だ。「母の恋愛」を真正面から描く物語は意外と少ないが、窪はここでも遠慮なく踏み込んでくる。
多くの子どもにとって、「母親」は自分のものだ。母が誰かに恋をしていると知ったとき、そこには裏切られたような感覚と、母にも一人の人間としての幸せを願う気持ちが入り混じる。この作品は、その矛盾した感情を、息子たちそれぞれの視点から丁寧にすくい取っていく。
一方の母親も、「母であること」と「女であること」の間で揺れる。夫の不倫に傷つきながらも、自分が新しい恋をすることに後ろめたさを感じる。その葛藤は、決してきれいごとでは片づかない。窪は、彼女の小さな嘘や自己正当化も包み隠さず描く。その正直さが、読んでいて苦しくもあり、救いでもある。
物語が進むにつれて、「家族」という枠組み自体のあり方が問われていく。血縁でつながっていれば家族なのか、一緒に住んでいれば家族なのか。それとも、お互いの弱さを引き受ける覚悟があるかどうかが重要なのか。答えは簡単には出ないが、登場人物たちの選択を追いかけることで、読者自身の家族観も揺さぶられる。
この本は、母親世代にも、子ども世代にもそれぞれ違った痛みで響くはずだ。自分の親の恋愛を想像したことがない人ほど、読後にしばらく親の顔が頭から離れなくなるかもしれない。逆に、子どもを持つ読者にとっては、「もし自分がこの母親だったら」と何度も自問することになるだろう。
8. 夏日狂想
『夏日狂想』は、大正から昭和、そして戦後へと移りゆく時代の中で、「書く女」たちが抱え続けた葛藤と情熱を描いた評伝的長編だ。窪作品の中では珍しく、歴史を題材にした重厚な構成になっている。物語は、女性が文学や芸術を職業として成立させることが極めて難しかった時代を背景に、多くの女性たちの人生を束ねていく。
読んでいて感じるのは「怒り」よりも「共鳴」だ。女性が自由に表現しようとすることは、今でこそ当たり前の権利のように思われがちだが、当時は家父長制度の中で抑圧され、経済的にも社会的にも自立が困難だった。そんな時代の中で書くことを諦めなかった女性たちの姿は、今のクリエイターや会社員の読者にも響く。SNSや副業で表現を続けている女性なら、彼女たちの迷いや焦りが痛いほど理解できるはずだ。
作中で描かれる女性たちは、皆どこか不器用で、時に身勝手で、誰かに甘えながらも独りで立とうとする。そのアンバランスさは、現代の女性読者にとっても馴染み深いリアリティを持つ。読みながら、ふと自分の人生のある時期と重なるエピソードが現れ、胸がひりつく瞬間が何度もある。
窪がこれを「評伝小説」として書いた意義は大きい。現実の女性作家たちが背負ってきた歴史を下敷きにすることで、フィクションとしての説得力が一気に増している。そして、歴史ものの重さを背負いながらも、文章は透明で読みやすい。夏の湿気のようにまとわりつく生々しさと、乾いた風のような自由の気配が交互に流れてくるような読書体験だった。
過去の女性たちが切り開いてくれた道の上を歩いているのだと気づいたとき、作品世界が急に現実と接続される。その瞬間に胸へ込み上げる感情は、読者の人生経験によって違うだろう。【書くこと】に関わるすべての人に手渡したい一冊だ。
9. アカガミ
『アカガミ』は、近未来の日本を舞台にしたディストピア小説で、窪美澄の作家性の中でも異色の存在だ。国が主導する結婚支援システム「アカガミ」によって、若者たちの恋愛や性交、結婚が管理される社会が描かれる。恋愛の自由が奪われた世界で、人は何を求めて生きようとするのか──読み進めるにつれて、その問いが喉に刺さって抜けなくなる。
恋愛や結婚が「自由に選べるもの」という前提が覆されるとき、幸福の形はどう変わるのか。アカガミ制度に従って淡々とパートナーを割り当てられる若者たちは、感情をどう扱えばいいのか分からない。好きでも嫌いでもない相手と、国家によって定められた幸福を目指すことの虚しさ。そこには、現実の婚活市場やマッチングアプリにも通じる「制度化された恋愛」の息苦しさがある。
物語の核には、「感情はコントロールできるものではない」という当たり前の事実が据えられている。制度がどれほど整備されても、人は誰かに惹かれたり、誰かに冷めたりする。それが人生の厄介さであり、美しさでもある。窪はこのテーマを、驚くほど冷静で、かつ残酷に描いている。
読みながら、未来というより「明日の日本」を見ているような感覚になった。恋愛や結婚における格差はすでに現実のものだし、国家が人口問題を理由に個人の生き方へ介入してくる未来も想像に難くない。そんな不気味なリアリティが、この作品の恐怖を増幅させている。
ディストピア小説として読むだけでなく、現代の婚活や恋愛の価値観に疲れている人にも刺さる。恋愛を「最適化」や「合理化」しようとする動きに息苦しさを感じているなら、この物語はその違和感の正体を照らしてくれるはずだ。
10. 朔が満ちる
『朔が満ちる』は、虐待を受け、父親を殺そうとした過去を持つ男性と、孤独を抱えた看護師の女性が互いの傷に触れていく物語だ。窪作品の中でもとくに「痛み」の描写が鋭い一冊で、読んでいて胸が軋むような場面が何度も訪れる。
主人公の男性は、過去の暴力によって時間が止まったまま大人になってしまったような存在だ。周囲から見れば「加害者」であり、同時に「被害者」でもある。その二面性は、窪がこれまで一貫して描いてきたテーマでもある。「人はひとつのラベルでは語れない」という、彼女の強い姿勢がここにもある。
一方、看護師の女性は、患者の死を何度も経験する中で、自分自身の感情が摩耗していく感覚に悩んでいる。誰かの命を支える仕事をしながら、自分の生活は荒れていく。その矛盾が、あまりにもリアルだ。医療現場に関わる読者なら、何度も心がざわめく瞬間があるだろう。
二人が少しずつ心を開いていく過程は、恋愛というより「共鳴」に近い。窪は決して彼らを癒さないし、救わない。むしろ、お互いの傷を見せ合うことでようやく立ち上がれるのだと示す。その姿が美しくもあり、救いようがないようにも感じられる。
読後に残るのは、希望よりも静かな決意に近い感情だ。傷は消えないし、過去は変えられない。それでも、この二人は明日も生きていくのだろうと信じられる。その微かな光が、この物語を暗闇のまま終わらせない。
11. 我らがパラダイス
高級老人ホームを舞台にしたこの作品は、「介護格差」「老いの贅沢」「家族の無関心」など、現代日本の老人ケアが抱える問題を突きつけてくる社会小説だ。窪作品を読み込んでいる読者なら、この設定がいかにも彼女らしいと感じるだろう。
高級老人ホームという場所には、豊かな老人と、家族に捨てられた老人が混在する。金銭的に余裕がある入居者は、理不尽な要求を職員へ突きつける。一方で、職員たちは過酷な労働条件に耐えながら、なんとか日々を乗り切ろうとする。この格差が物語の縦軸になっている。
注目したいのは、職員たちの視点が丁寧に描かれている点だ。彼らは決して「善人」ではない。利用者への不満を溜め込み、同僚との軋轢に苦しみ、家族の介護と仕事のダブルケアで心が折れそうになる。それでも、誰かの顔を拭いてあげたり、話し相手になったりする中で、「自分はここにいるべきなのかもしれない」と揺れる。
一方の老人たちも、単なる弱者として描かれていない。富を持つ者の傲慢さ、家族への未練、過去の後悔……。老いは決して美しくない。しかし、窪はその醜さを「人間の自然な姿」として描き、どこか愛おしささえ感じさせる。
読み進めるほど、「パラダイス」というタイトルが皮肉な響きを帯びていく。贅沢な設備と豪華な食事を備えた施設にいても、心が満たされない人は満たされない。逆に、貧しくても誰かの気遣いが心を救うこともある。何を「楽園」と呼ぶのか、読者は思わず考え込んでしまう。
介護職や医療職の読者には刺さりすぎるほど痛いが、老親を抱える世代にも必読の一冊だ。高齢化社会を生きるすべての人にとって、「明日の自分」を考えさせられる物語になっている。
12. アニバーサリー
『アニバーサリー』は、結婚記念日をテーマにした連作短編集で、夫婦や恋人、家族の微妙な距離感を描き出していく作品だ。誰かと長く暮らすということは、祝うべき瞬間と、思い出したくない瞬間が入り混じる。その揺れを、窪は見事に言葉へ落とし込んでいる。
お祝いの日なのに口論になったり、感謝を伝えたくても素直に言えなかったり、プレゼント選びで地雷を踏んでしまったり……。どのエピソードも、読者自身の生活にそのまま重なってくる。特別なドラマがあるわけではないが、「ああ、こういうことってあるよな」と思わず息をつく瞬間が何度も訪れる。
夫婦関係の「冷め」にも「熱」にも偏りすぎず、その中間の微妙な体温を描くのが窪の強みだ。嫌いじゃない、でも好きと言い切れるほどでもない。別れたいわけでもないけれど、このままでいいのか迷う。そんな曖昧な位置にいる夫婦の空気感が、恐ろしくリアルだ。
個人的には、ある中年夫婦が「これからも一緒にいるべきか」を考え直すエピソードが胸に残った。長く連れ添ったのに、相手の気持ちが分からなくなる瞬間は、夫婦だけでなく友人関係にも当てはまる。記念日という「節目」が、日常に埋もれていた感情を浮き彫りにしていく。
結婚生活に悩んでいる人はもちろん、同棲中のカップルにも勧めたい。恋愛を「イベント」で測ってしまいがちな世代には、とくに刺さるだろう。
13. 水やりはいつも深夜だけど
タイトルの通り、この作品には「深夜」という時間帯がよく似合う。親と子、それぞれが抱える生きづらさが、薄暗い部屋に置かれた観葉植物のように静かに広がる短編集だ。
育児疲れで感情が枯れてしまった母親、親の期待に押しつぶされる中高生、介護を強いられる若者、家族に甘えることができない大人たち……。どのエピソードにも「ほんの少しの孤独」が染み込んでいる。窪はその孤独をドラマチックに描かず、日常の中に忍び込んだ影のように扱う。
植物の水やりを「深夜」にやる理由は、人に見られたくないからだ。自分の弱さや不器用さを隠しながら生きている人ほど、この作品の世界に居心地の良さを感じるはずだ。誰にも言えない感情を、深夜の静けさの中でそっと確かめているような読書体験になる。
短編集としては読みやすいが、どの話も心にズシンとくる。一話読み終えるごとに照明を落としたくなる。深夜の台所でコップ一杯の水を飲みたくなる。そんな類の本だ。
14. よるのふくらみ
幼馴染の兄弟と、その間で揺れる女性の関係を、身体の交わりと感情のすれ違いを通して描いた作品。性愛をテーマにしているが、決して官能小説ではない。むしろ、性を通して「他者とつながることの難しさ」を描く文学寄りの作品だ。
兄弟の間に流れる競争心や嫉妬、幼い頃からの愛憎のバランスが、女性との関係によってさらに複雑化していく。恋愛の三角関係というより、人間の根源的な欲望と承認欲求がぶつかり合う物語に近い。読んでいて何度も息がつまる。
窪らしいのは、性描写の扱いだ。エロティックでありながら、「気持ちよさ」より「痛み」のほうが勝っている。身体が触れ合うことで、むしろ孤独が強調される瞬間がある。その描写があまりにも繊細で、読者としては言葉にできない感情に襲われる。
物語としての起伏は緩やかだが、心理描写が濃密なので読み応えは十分。自分の中にある嫉妬や後ろめたさを思い出して、しばらくページがめくれなくなる瞬間があった。
恋愛小説として読むより、「人間の欲望の形」を観察するような気持ちで読むと、作者の筆の鋭さがよく分かる。読後にずっしりくる一冊だ。
15. タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース
タイトルからして不穏なこの一冊は、心を病んだ人々と、彼らに寄り添う精神科医・カウンセラー夫婦の姿を描いた連作集だ。「死亡時刻(Time of Death)」と「出生日時(Date of Birth)」という二つの時間が並んでいることからも分かるように、生と死のあいだを揺れ動く人間の心を見つめ続ける物語になっている。
出てくるのは、うつ病、不安障害、依存症、トラウマ……診断名で分類すれば簡単だが、窪はそんなラベルに興味がない。彼女が描くのは、「診断名の裏で、その人がどんな日々を生きてきたのか」という物語のほうだ。患者たちは病気の象徴ではなく、仕事に挫折したり、恋愛に傷ついたり、家族との関係に悩んだりする、ごく普通の人間として立ち上がる。
興味深いのは、精神科医夫婦自身もまた、完璧な「専門家」ではないという点だ。人を救おうとしながら、自分たちの関係はどこかすれ違っている。患者と向き合ううちに、自分の中にある歪みや傷にも気づいてしまう。その揺れが、物語の奥行きを生んでいる。
読んでいて何度か、胸の奥がざわついた。ここに描かれているのは、「病んでいる側」と「支える側」という単純な構図ではない。支える人もまた、いつ崩れてもおかしくないギリギリの場所に立っている。医療や福祉の現場にいる読者なら、自分自身の疲労や迷いを重ねてしまうだろう。
それでもこの本は、絶望だけを残して終わるわけではない。患者と医師の間に、ごく短い瞬間だけ生まれる信頼や、言葉にならない理解の気配が、ところどころにひっそりと置かれている。その瞬間が、読者にとっても救いになる。奇跡的な回復ではなく、「今日は何とか生き延びた」という小さな勝利が、静かに積み重なっていく。
メンタルの不調を抱えている人にとっては、かなり生々しい内容かもしれない。無理に元気を出させるタイプの本ではないからこそ、ある程度落ち着いたタイミングで、自分の歩いてきた道を振り返るような気持ちで読むといい。音で物語を追いたい人は、移動中にAudibleで耳から物語を浴びるように聴くと、また違う「距離感」でこの世界を見られると思う。
16. いるいないみらい
『いるいないみらい』は、AIやVRが日常に溶け込んだ近未来を舞台に、人間の感情や記憶のあり方を問い直すSF的短編集だ。窪美澄といえばリアルな現代劇の印象が強いが、この作品ではテクノロジーが人の心をどのように変えていくか、というテーマに大胆に踏み込んでいる。
しかし、ガジェットやシステムの設定が細かく語られるわけではない。あくまで焦点は「人」に当たっている。AIに最適化されたマッチングで恋愛を選ぶ若者、亡くなった家族の記憶データに依存してしまう中年、VR空間にだけ自分の居場所を感じる子どもたち……。どの物語にも、「テクノロジーを使う側」と「使われる側」の境界がきわどく揺れる瞬間が描かれている。
印象的なのは、未来を描いているのに、どこか既視感があることだ。スマホやSNSに依存する今の生活と地続きなので、登場人物の感情は決して遠い世界のものではない。むしろ、自分自身がすでに半分くらいこの物語の中に足を踏み入れているのではないか、と感じるほどだ。
「いる/いない」という対立は、存在そのものだけでなく、「ここに心があるのか/ないのか」という問いにもつながっていく。誰かがそばにいるのに、まったく通じ合っていない感覚。逆に、物理的には離れているのに、誰より近く感じる不思議さ。テクノロジーがそれを増幅させているのか、可視化しているだけなのか、それは読み手に委ねられている。
SFというラベルに引いてしまう人もいるかもしれないが、中身は紛れもなく「窪美澄の小説」だった。生身の心がテクノロジーにぶつかって傷つく、その瞬間を描く筆致は、他の作品と一貫している。今の生活にスマホやネットが欠かせない人ほど、自分の未来を覗き込んでいるような気分になる一冊だ。
17. すみれ草
ラストを飾る『すみれ草』は、夫の死後に残された妻と、その愛人、それぞれの視点から「愛すること」の意味を問い直す物語だ。死によって終わったはずの三角関係が、むしろそこから本当の姿を現し始める、という構造になっている。
夫を失った妻は、悲しみと同時に、夫への怒りや、自分が見ようとしてこなかった現実に直面させられる。一方の愛人は、喪失感に加えて、社会的には決して「正式な遺族」として扱われない痛みを抱える。二人の女性は対立しながらも、どこか似た孤独を分かち合っているようにも見える。
この作品の魅力は、「妻こそ正義」「愛人は敵」といった単純な図式に回収されないところだ。窪はどちらの女性にも同じだけの重さを与え、読者がどちらにも肩入れし、どちらにも共感してしまうように物語を進めていく。そのバランス感覚が見事だ。
また、「死」が必ずしも物語の終わりではないことを、これほど静かに、しかし力強く描いた作品も珍しい。人が亡くなったあとに残されるのは、悲しみだけではない。安堵、解放感、後悔、怒り、嫉妬、未練。その複雑な感情の渦を、すみれ草の小さな花びらのようなささやかな描写で包み込んでいく。
大切な人を亡くした経験がある読者には、ときにえぐるような読書体験になるだろう。それでも、この物語の終盤に差し込む一筋の光は、派手さこそないが、とても誠実なものに感じられる。亡くなった人との関係を、静かに自分の中で「置き直す」ために読む一冊として、大切にしたくなる。
18. 夜空に浮かぶ欠けた月たち (角川書店単行本)
この作品を読みはじめたとき、胸の奥にひんやりした風が入り込んでくるような感覚があった。タイトルにある「欠けた月」は、完璧ではない人生をそのまま象徴している。登場人物たちはみな欠けている。誰かを失ったり、将来を見失ったり、自分を肯定できなかったり……。けれど、その欠けは決して恥ではなく、静かに抱えていくしかない事実だと語りかけてくる。
物語を通して特徴的なのは、彼らの「沈黙」だ。生きづらさを抱えた人ほど、自分の悲鳴を言葉にできない。その沈黙の時間が長く描かれることで、読者は彼らの呼吸の乱れまで感じ取れてしまう。窪の文章は決して説明的にならず、ほんの些細な仕草や間を描くことで、彼らの内側に溜まった“言えない感情”を読者へ渡してくる。
読み終えると、欠けている月たちが“それでも夜空に浮かび続ける”という事実がじんわりと心に残る。完璧じゃなくていい、すべてを治さなくていい。欠けたまま進んでいく姿に、寄り添うような優しさを感じる一冊だ。
19. 宙色のハレルヤ (文春e-book)
『宙色のハレルヤ』は、窪作品の中でも特に“救いの輪郭”が柔らかい物語だ。宙を見上げるとき、人は無意識に「いまここではない場所」を想像する。物語の登場人物たちもまた、いまの人生に満足しているわけではない。それでも、時折ふっと訪れる光のような瞬間を感じ取ろうと懸命に生きている。
窪が描く幸福は、決して大袈裟なドラマの中に存在しない。仕事中の静かな一呼吸、誰かにもらった短いメッセージ、電車の窓に映った自分の疲れた顔。それらが束になったとき、初めて「まだ生きていける」と思えるような優しさを持っている。この作品では、その小さな救いが“ハレルヤ”と呼ぶにふさわしいほど澄んでいる。
自分を好きになれないまま大人になってしまった人、誰かと比べることでしか自分を測れない人に強く刺さる。読み終えたあと、ふっと夜空を見上げたくなる。そこにあるのは、派手ではないが確かな光だ。
20. 私は女になりたい (講談社文庫)
タイトルのインパクトとは裏腹に、この作品の核心は非常に繊細だ。「女であること」をめぐる痛み、戸惑い、社会の期待、そして自分自身の輪郭の揺らぎ……。窪は“性”をテーマにしながら、単純なジェンダー論へ落とし込まず、あくまで「個人」の物語として描ききる。
主人公の揺れ動く感情は、読者の心に沈殿していた言葉にならない感覚を呼び覚ます。社会が押しつける“理想の女性像”と、自分の内側から自然に湧き出てくる“本当の私”の間にある断絶。その断絶が丁寧に描かれているからこそ、自分の中の曖昧さを許す気持ちにもつながっていく。
特に印象的なのは、主人公がふとした瞬間に見せる“弱さ”だ。強く見せたいのに強くなれない、優しく振る舞いたいのに優しさがこぼれ落ちてしまう。窪はその矛盾を責めず、ただ淡々と描く。それが逆に読者へ「生きているだけで十分だ」とささやく。
ジェンダーに悩んだ経験がある人はもちろん、自己肯定感が揺れるすべての読者に読んでほしい作品だ。
21. 朱より赤く 高岡智照尼の生涯 (小学館文庫 く 18-1)
実在の人物・高岡智照尼を描いた歴史小説であり、窪美澄の文学的挑戦ともいえる一冊だ。智照尼は、明治から昭和にかけて激動の時代を生きた女性で、尼僧としての精神性と、ひとりの人間としての苦悩が常にせめぎ合っていた。
歴史背景が重い作品だが、窪の筆は驚くほど澄んでいる。苦境に置かれた智照尼が静かに信念を貫こうとする姿には、現代を生きる私たちが抱える葛藤と通じる部分が多い。家族の期待、社会の役割、宗教的使命……。どれも自分で選んだようで、実は選ばざるを得なかったものだ。
特に心を打つのは、智照尼が自分の内側にある“赤”を見つめ続ける場面だ。情念、怒り、愛、悲しみ……それらすべてが混ざり合った濃い赤。朱よりも濃く、鮮烈な赤。この赤を抱えたまま前に進む姿に、強さではなく「深さ」を感じた。
歴史小説としても読み応えがありつつ、精神の物語としても胸に響く。ゆっくり読んで自分の思考が静まるのを味わいたい作品だ。
22. 給水塔から見た虹は (集英社文芸単行本)
給水塔という、日常にありながらほとんど意識しない場所をタイトルに据えた時点で、もう窪らしい。物語は、都市の片隅に生きる人々が“見上げたときにだけ見える景色”をテーマに進んでいく。虹は象徴的なモチーフだが、そこに込められる希望は決して派手ではない。むしろ、見落としてしまいそうなほど静かだ。
登場人物たちは、誰もがどこか乾いている。仕事に追われて心が擦り切れた大人、家族との距離に疲れた若者、もう一度だけ人生を信じたいと願う中年……。彼らの乾きは、給水塔に貯められた水の静けさと重なってみえる。
物語の中盤で、“虹”が象徴として現れる場面がある。はっきり見えるわけではなく、角度によっては見えない。その曖昧な虹が、この作品の核心だ。希望はいつも見えるとは限らないし、誰もが同じように見られるわけでもない。それでも、ふとした瞬間に確かに存在している。
読み終えたあと、自分の人生にも“見えなかった虹”があったのではないかと考えさせられる。静かだが美しい余韻が続く一冊だ。
窪美澄作品と一緒に使いたい関連グッズ・サービス
窪美澄の本は、じっくり感情と向き合いたいタイプの作品が多い。読書体験を少しだけ快適にするための相棒も、ここでいくつか挙げておきたい。
1. 電子書籍サービス(Kindle端末+サブスク)
夜中に目が冴えてしまったとき、『夜に星を放つ』や『水やりはいつも深夜だけど』のような短編集を少しずつ読み進めるのに、軽い電子書籍端末は相性がいい。紙のページをめくる音を立てたくない夜でも、そっと親指だけでページが進んでいく。サブスクでまとめ読みしたいなら、Kindle Unlimitedを一度体験してみると、「今日はどの窪作品に潜るか」を気分で選びやすくなる。
2. オーディオブック(Audibleなど)
家事や通勤のあいだ、「活字を追う余裕はないけれど物語は浴びたい」というときがある。そんなとき、Audibleのようなオーディオブックサービスは、かなり頼もしい。窪作品は登場人物の会話が生々しいので、声優の読み上げで聞くと、また違う角度から物語の温度が伝わってくる。洗い物をしながら、登場人物たちのやりとりに思わず手が止まる、そんな瞬間も悪くない。
3. 小さめの読書ノート
読んでいて刺さった台詞や場面を、短くメモしておくためのノートが一冊あると、窪作品との付き合い方が少し変わる。読後に見返すと、「あのとき自分はこんな言葉に救われたんだな」と後から気づくことができる。感情のログを残しておくことで、自分の変化も見えやすくなる。
窪美澄を読むならどれから?──全体のまとめ
窪美澄の主要作22冊を眺め直してみると、一貫して見えてくるものがある。 それは、「人はそんなに立派には生きられないけれど、それでも生きていく」という静かな前提だ。喪失、性の傷、家族の歪み、老い、格差、メンタルの不調。どの作品もテーマだけ聞くと重い。それなのにページを閉じたあと、ほんの少しだけ体が軽くなるのは、登場人物たちが誰も正しくないまま、それでも明日へ歩いていくからだと思う。
どこから読んでもいいが、目的別に選ぶなら、こんなふうに考えるのもありだ。
- まず世界観に触れてみたいなら:『夜に星を放つ』『ふがいない僕は空を見た』
- 仕事やキャリアに悩んでいるなら:『トリニティ』『我らがパラダイス』『クローバーナイト』
- 家族や母性の揺らぎに向き合いたいなら:『ははのれんあい』『やわらかな麻の葉』『じっと手を見る』
- 近未来や社会の構造から考えたいなら:『アカガミ』『いるいないみらい』『カトレアの棺』
- 喪失や喪の作業をゆっくり見つめたいなら:『タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース』『すみれ草』
どの本も、読みながら自分の人生のどこかの場面を思い出さずにはいられない。しんどいときほど、ページをめくる手は重くなるが、その重さごと抱えて読んでいい作家だと感じる。 いつか、自分の心が少し揺れたときに、「そういえば窪美澄のあの本に似た気持ちが描かれていたかもしれない」と思い出せたら、そのときがまた新しい読書の入口になる。
よくある質問(FAQ)
Q1. どの作品から読めばいいか迷う。初めての一冊におすすめは?
テーマの重さを考えると、いきなり『ふがいない僕は空を見た』に突っ込むと、かなり胃がもたれる読書になるかもしれない。まずは短編集『夜に星を放つ』から始めるのがおすすめだ。一話ごとに区切りがあり、喪失と再生という窪作品の根っこのテーマが凝縮されている。次の候補としては、『クローバーナイト』や『我らがパラダイス』のように複数人物の群像劇になっているものを選ぶと、自分と距離を取りながら読める。慣れてきたら、『さよなら、ニルヴァーナ』や『タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース』のような重いテーマに挑むといい。
Q2. 窪美澄の作品は「重そう」で怖い。心が弱っているときに読んでも大丈夫?
正直なところ、心が限界まで削れている時期に読むには、かなり負荷の大きい作品も多い。とくに虐待や性暴力、メンタルの不調を直接的に扱う作品は、トリガーになる可能性もある。ただ、「自分のしんどさを言語化してくれる本」を探しているなら、窪作品はとても心強い味方になる。少しだけ余裕があるタイミングを選んで、短編から様子を見るのがいい。途中で読むのをやめてもかまわないし、何年か置いてから再挑戦してもいい。窪の物語は、読者の時間に付き合ってくれるタイプの本だ。
Q3. 子育て中でも読める? 時間がとれないときの付き合い方が知りたい。
まとまった読書時間がとれないなら、短編集や連作短編との相性がいい。『夜に星を放つ』『水やりはいつも深夜だけど』『アニバーサリー』あたりは、一話ごとに完結しているので、子どもが寝たあとや家事の合間に少しずつ読むことができる。電子書籍やオーディオブックを組み合わせれば、スマホ一台でいつでも物語に潜れる。ほんの3ページだけ読む、という付き合い方でもいい。窪作品は一気読みしなくても、断片が心に残り続けるタイプの小説なので、短い時間の積み重ねでも十分に世界に浸れる。
Q4. 他のどんな作家が好きな人に、窪美澄は刺さりやすい?
人間関係の痛みや性の揺らぎを濃密に描く島本理生、地方都市や家族のほころびを静かに見つめる桜木紫乃、社会の片隅で生きる人々をすくい上げる桜庭一樹あたりが好きな読者には、かなり高い確率で窪作品も刺さると思う。また、介護や医療、福祉の現場で働いている人なら、『じっと手を見る』や『我らがパラダイス』のリアルさに驚くはずだ。逆に、「日常のしんどさにはあまり触れたくない」「物語には徹底した逃避を求める」というタイプの読者には、体力がいる作家かもしれない。
関連記事
- 海老沢泰久のおすすめ本
- 小池真理子のおすすめ本
- 乃南アサのおすすめ本
- 坂東眞砂子のおすすめ本
- 篠田節子のおすすめ本
- 車谷長吉のおすすめ本
- 藤堂志津子のおすすめ本
- 佐藤賢一のおすすめ本
- 金城一紀のおすすめ本
- 山本文緒のおすすめ本
- 藤田宜永のおすすめ本
- 山本一力のおすすめ本
- 乙川優三郎のおすすめ本
- 村山由佳のおすすめ本
- 熊谷達也のおすすめ本
- 朱川湊人のおすすめ本
- 森絵都のおすすめ本
- 松井今朝子のおすすめ本
- 桜庭一樹のおすすめ本
- 井上荒野のおすすめ本
- 北村薫のおすすめ本
- 白石一文のおすすめ本
- 唯川恵のおすすめ本
- 阿部龍太郎のおすすめ本
- 桜木紫乃のおすすめ本
- 朝井まかてのおすすめ本
- 黒川博行のおすすめ本
- 東山彰良のおすすめ本
- 荻原浩のおすすめ本
- 恩田陸のおすすめ本
- 佐藤正午のおすすめ本
- 島本理生のおすすめ本
- 大島真寿美のおすすめ本
- 川越宗一のおすすめ本
- 馳星周のおすすめ本
- 澤田瞳子のおすすめ本
- 今村翔吾のおすすめ本
- 窪美澄のおすすめ本
- 垣根涼介のおすすめ本
- 永井紗耶子のおすすめ本
- 河崎秋子のおすすめ本
- 一穂ミチのおすすめ本
- 麻布競馬場のおすすめ本
- 岩井圭也のおすすめ本
- 中村彰彦のおすすめ本